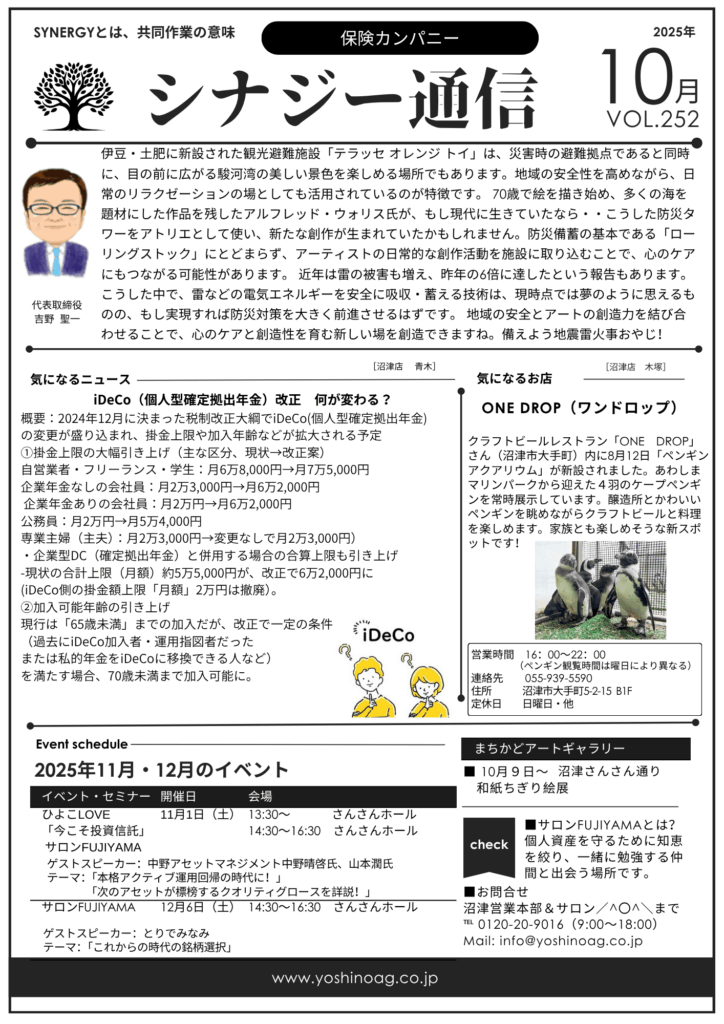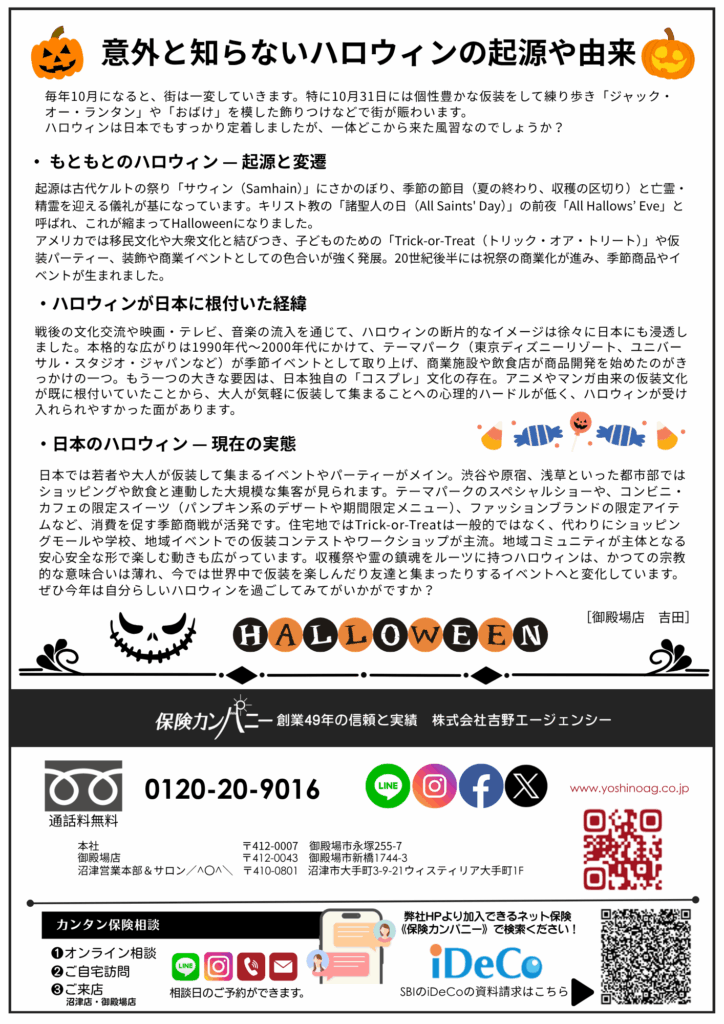自営業・会社員・学生も注目!iDeCo掛金上限アップ&70歳未満まで加入可能へ【シナジー通信2025年10月】
iDeCo(個人型確定拠出年金)の制度改正、何が変わる?
2024年12月に決定した税制改正大綱にて、iDeCo(個人型確定拠出年金)の制度変更が盛り込まれました。
これにより、掛金の上限額や加入できる年齢などが拡大される予定です。
主な変更点は以下の2つです。
① 掛金上限の大幅な引き上げ
加入区分に応じて、毎月の掛金の上限額が以下のように引き上げられます。
- 自営業者・フリーランス・学生
- 現状:月6万8,000円 → 改正後:月7万5,000円
- 企業年金なしの会社員
- 現状:月2万3,000円 → 改正後:月6万2,000円
- 企業年金ありの会社員
- 現状:月2万円 → 改正後:月6万2,000円
- 公務員
- 現状:月2万円 → 改正後:月5万4,000円
- 専業主婦(主夫)
- 現状:月2万3,000円 → 変更なし
【補足】企業型DC(確定拠出年金)と併用する場合
企業型DCとiDeCoを併用する場合の合算上限額も引き上げられます。
これまでiDeCo側の掛金は月額2万円までという上限がありましたが、この制限が撤廃されます。
- 現状の合計上限(月額):約5万5,000円 → 改正後:月6万2,000円
② 加入可能年齢の引き上げ
現行制度では「65歳未満」までの方が加入できましたが、改正後は一定の条件を満たす場合に「70歳未満」まで加入可能になります。
<対象となる方の条件例>
- 過去にiDeCoの加入者または運用指図者であった方
- お勤め先の私的年金をiDeCoに移換できる方 など
防災×アート×自然が融合する新しい避難施設のかたち
駿河湾を望む観光避難施設「テラッセ オレンジ トイ」
伊豆・土肥に新設された観光避難施設「テラッセ オレンジ トイ」は、災害時の避難拠点であると同時に、目の前に広がる駿河湾の美しい景色を楽しめる場所でもあります。地域の安全性を高めながら、日常のリラクゼーションの場としても活用されているのが特徴です。
アートと防災の新しい可能性
70歳で絵を描き始め、多くの海を題材にした作品を残したアルフレッド・ウォリス氏が、もし現代に生きていたなら・・こうした防災タワーをアトリエとして使い、新たな創作が生まれていたかもしれません。防災備蓄の基本である「ローリングストック」にとどまらず、アーティストの日常的な創作活動を施設に取り込むことで、心のケアにもつながる可能性があります。
増加する雷被害と未来の防災技術
近年は雷の被害も増え、昨年の6倍に達したという報告もあります。こうした中で、雷などの電気エネルギーを安全に吸収・蓄える技術は、現時点では夢のように思えるものの、もし実現すれば防災対策を大きく前進させるはずです。
心のケアと創造性を育む新しい防災の場
地域の安全とアートの創造力を結び合わせることで、心のケアと創造性を育む新しい場を創造できますね。備えよう地震雷火事おやじ!
セミナー サロンFUJIYAMA 資産を守り、未来を拓く
個人資産を守るための知識と知恵を共有し、共に学ぶ仲間と出会える場所です。静岡県内外から多様な参加者が集まり、活発な情報交換と交流が生まれています。セミナー後には、参加者同士の親睦を深める懇親会もご用意。資産運用や防衛に関心のある方なら、どなたでもお気軽にご参加いただけます。
参加者の声
- 「様々な情報交換を通じて、視野が大きく広がりました。」
- 「同じ悩みや目標を持つ仲間と出会え、心強く感じました。」
- 「専門家から具体的な対策を学べ、今後の資産設計に役立ちそうです。」
2025年11月1日(土)〇14:30~16:30
ゲストスピーカー:中野アセットマネジメント中野晴啓さん、山本潤さん
テーマ:「本格アクティブ運用回帰の時代に!」 「次のアセットが標榜するクオリティグロースを詳説!」
会場:さんさんホール
2025年12月6日(土)〇14:30~16:30
ゲストスピーカー:とりでみなみさん
テーマ:「これからの時代の銘柄選択」
会場:さんさんホール
お申し込みはこちら:資産形成セミナー
お問合せは:吉野エージェンシー 沼津営業本部&サロン/^〇^\まで
℡ 0120-20-9016(9:00~18:00) Mail: info@yoshinoag.co.jp
沼津さんさん通り「まちかどアートギャラリー」
10月のまちかどアートは、和紙ちぎり絵展
沼津駅南口、さんさん通りを訪れた際には、ぜひアートの世界をお楽しみください。
気になるお店 ONE DROP(ワンドロップ)
クラフトビールレストラン「ONE DROP」さん(沼津市大手町)内に8月12日「ペンギンアクアリウム」が新設されました。あわしまマリンパークから迎えた4羽のケープペンギンを常時展示しています。醸造所とかわいいペンギンを眺めながらクラフトビールと料理を楽しめます。家族とも楽しめそうな新スポットです!
営業時間 16:00~22:00 (ペンギン観覧時間は曜日により異なる)
連絡先 055-939-5590
住所 沼津市大手町5-2-15 B1F
定休日 日曜日・他
意外と知らないハロウィンの起源や由来
毎年10月になると、街は一変していきます。特に10月31日には個性豊かな仮装をして練り歩き「ジャック・オー・ランタン」や「おばけ」を模した飾りつけなどで街が賑わいます。
ハロウィンは日本でもすっかり定着しましたが、一体どこから来た風習なのでしょうか?
もともとのハロウィン — 起源と変遷
起源は古代ケルトの祭り「サウィン(Samhain)」にさかのぼり、季節の節目(夏の終わり、収穫の区切り)と亡霊・精霊を迎える儀礼が基になっています。キリスト教の「諸聖人の日(All Saints’ Day)」の前夜「All Hallows’ Eve」と呼ばれ、これが縮まってHalloweenになりました。
アメリカでは移民文化や大衆文化と結びつき、子どものための「Trick-or-Treat(トリック・オア・トリート)」や仮装パーティー、装飾や商業イベントとしての色合いが強く発展。20世紀後半には祝祭の商業化が進み、季節商品やイベントが生まれました。
ハロウィンが日本に根付いた経緯
戦後の文化交流や映画・テレビ、音楽の流入を通じて、ハロウィンの断片的なイメージは徐々に日本にも浸透しました。本格的な広がりは1990年代〜2000年代にかけて、テーマパーク(東京ディズニーリゾート、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンなど)が季節イベントとして取り上げ、商業施設や飲食店が商品開発を始めたのがきっかけの一つ。もう一つの大きな要因は、日本独自の「コスプレ」文化の存在。アニメやマンガ由来の仮装文化が既に根付いていたことから、大人が気軽に仮装して集まることへの心理的ハードルが低く、ハロウィンが受け入れられやすかった面があります。
日本のハロウィン — 現在の実態
日本では若者や大人が仮装して集まるイベントやパーティーがメイン。渋谷や原宿、浅草といった都市部ではショッピングや飲食と連動した大規模な集客が見られます。テーマパークのスペシャルショーや、コンビニ・カフェの限定スイーツ(パンプキン系のデザートや期間限定メニュー)、ファッションブランドの限定アイテムなど、消費を促す季節商戦が活発です。住宅地ではTrick-or-Treatは一般的ではなく、代わりにショッピングモールや学校、地域イベントでの仮装コンテストやワークショップが主流。地域コミュニティが主体となる安心安全な形で楽しむ動きも広がっています。収穫祭や霊の鎮魂をルーツに持つハロウィンは、かつての宗教的な意味合いは薄れ、今では世界中で仮装を楽しんだり友達と集まったりするイベントへと変化しています。
ぜひ今年は自分らしいハロウィンを過ごしてみてがいかがですか?
■シナジー通信2025年10月号を発行しました!
「シナジーSynergy」とは、共同作業の意味です。252回の発行となりました。沼津店・御殿場店でも入手いただけます。